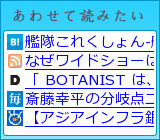[PR]
投稿日:2025年10月10日(金)
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
だから何だの先へ
投稿日:2008年10月01日(水)
朝起きてコメントの返信をしたり何か書いたりしようと思ったらBlogが朝9時までメンテナンスだった。ところで、こういう日記形式のBlogって、普通は言葉にしないものをあえて書いているわけだよね。小説を書けない悩みだの創作のこだわりだのなんてのは誰もが持っている。それなのに自分だけが特別であるかのようにとうとうとまくしたてているさまは、人によっては不快以外のなにものでもない。思慮のある人ならこう思っているかもしれない。まずその口を閉じろ、と。
読みモノとしてのBlogを成功させるコツはまず自分を消すことだ。誰が言ったか知らない。誰も言っていないかも知れない。俺の直感にすぎないのかもしれないが、文章とはそれ自身に意味があるのであって、それを書いている人間の自己主張など読者にとってはどうでもいいのだ。書き手の自己主張が文章じゃないのかと思われるかも知れない。しかし、よくできた文章というのは必ずしも書き手の自己主張ではないと思う。自己主張が褒められるのは、おそらくは学校教育における作文だけだ。作文の読み手は先生と親ぐらいのものだろう。しかし、Blogにしても小説にしてもそこには必ず読者がいる。実在しなくてもいい。誰一人読まないのであっても、文章が文章として成立できるのは読者がいるからだ。ああ、自分でもわけがわからない。
カンタンに言ってしまえば、読者にとって書き手がどう考えているかなんてことはどうでもいいってことだ。おまえのことなんか知ったこっちゃねーよ、だね。書き手ってのは、大仰にブンガクについて悩んで見せたり、言葉の乱れを嘆いて見せたり、あの手この手で結局は自己主張したいだけだったりする。俺ら素人が素人のままでいる一番の理由は、文章に対する姿勢が、視線が、個人的な範囲を超えていないからではないだろうか。
ここで、安易に「自分」という言葉を使ったことに少し心配する。個人的なことを書いても面白い人はいるし、自分を消したら逆に個性がなくなってしまうのではないか、という声も聞こえてくる。「個性」という言葉もたちが悪いな。こういう単純で身近な言葉にこそ恐ろしいモノが潜んでいるのだから怖い。それはともかく、逃げているわけにもいかないから、俺のもてる力で真っ正面から説明してみる。たまには、がんばる。
安っぽい箴言めいた言葉を思いついた。こんなのはどうだろう。
自分を書くのではない。自分を通して書くのだ。
なんのこっちゃ。うまくいえねぇ。というか、いえると思っているのか、俺は。何と戦っているのだ。ああ、助けて。
ひらめいた。きた。おりてきた。こんなのはどうだろう。
たとえば、空について書くとする。俺ら素人は、空を見て美しいと思った自分を書きたがる。空を見て美しいと思える美しい自分をアピールしたいだけだ。しかし、プロは違う、と思う。空を見て美しいと思っている自分を書くことで、空の美しさを表現する。自分というのは、空の美しさを書くための道具のようなものにすぎない。
この喩えはよくないなあ。こんなのだったらどうだろう。
たとえば、社会について書くとする。俺ら素人は、社会のなかで苦しんでいる自分自身を書きたがる。こんなにも苦しんでいる自分を見てください、と。しかし、プロは違う。社会のなかで苦しむ自分を書くことによって、社会そのものを表現する。
これって、三田誠広氏の本に書いてあったことと同じな気がする。違うかも知れないけど。無意識のパクリか。
最初に戻るけれど、いくら「このBlogは日記です」と逃げを打ってあるとしても、やはりまっとうな文章として存在させるには読者について考えないとならないな。創作に関する悩みを書くことで、ただ自分のことを書きたいだけなら、それはよくないだろう。そうではなく、悩んでいる自分を通して、創作に関する「何か」を読者に伝えないとならない。それが、先に書いた「自分を消す」ってことなんだけど、俺の表現の限界だ。
寝る。
いや、寝ないけど。
言葉を得るために言葉を捨てる
投稿日:2008年09月26日(金)
俺は今でもこだわっているのだがどうにもうまく説明できない。ただの言葉遊びと思われるかも知れない。だけど、何かの本にああこれだと思う記述があったはずなのだ。それを探していた。
で、やっと発掘した本のなかからみつけた。昔読んだ本だ。売らずに残っていた。小説じゃなくて詩の本だけれども、黒田三郎氏の『詩の作り方』にこう書かれている。以下引用。
T・E・ヒュームは比喩的表現について述べ、「われわれの多くは、ものをそのあるがままに見ることはなく、ただ、言語として具象化されている、ありあわせの類型を見るだけである」と言っています。ことばというものは、表現するときだけでなく、存在を見るときにさえ、人間とものとの間に立ちはだかるのです。
ヒュームは、この二重の困難が詩人にあることを示しています。見る場合にも表現する場合にも、類型化し、習慣化したことばが障害となるということです。比喩的表現は、経験を直接に、リアルに、全部をそっくりそのまま伝えようとする役割をもっています。しかしそれ以前に、詩人は、ブーアスチンの言うマス・メディアの生んだ疑似イベント(できごと)のイメージや、ヒュームの言う習慣化し、類型化したことばの障壁から、みずからを解放しなければならないでしょう。(黒田三郎『詩の作り方』)
引用終わり。
先日書いた雑記の、ナトリウムランプという言葉を知ってしまったときの困惑もこれに近い。名前を知らなかったときは、夜の国道を照らすオレンジ色の灯りに様々なものを感じ取っていたが、ナトリウムランプという言葉を知ってからは、まず「ナトリウムランプ」という言葉が思い浮かぶようになってしまう。記憶の片隅にある幼い日に見たトンネルのオレンジ色の灯りも、長い果樹園の農道を抜けたときに目にする国道の灯りも、大雪の真夜中に見た幻想的なオレンジの世界も、油断するとみな一つの言葉にまとめられてしまう。それはナトリウムランプに限ったことではなく、自分の身の回りのもののほとんどが、同じように言葉による束縛を受けているのだ。何かをみたときに、まずそれの名前が頭に浮かぶのだが、そこで普通はストップしてしまう。そこから先に進めない。モノの名前だけではなく、名前の知っているこの世のありとあらゆる現象についてもそうだろう。
とはいいつつも、これはあくまでも詩を書くための理屈であって小説に適用されるべきものとは限らない。だいたい、俺はこんなことにこだわっているからいつまでたってもまともな小説が書けないのだ。
詩人は世界の純粋な観察者であろうとするけれども、小説家は虚構によって世界を造り替えようとする。前者の「世界」と後者の「世界」は指し示すものがかなり違うのだが、書いている俺自身でもたぶんわかっていない。ただ、詩を書いたことのある人ならなんとなくわかるのではないだろうか。その「なんとなく」の壁がぶち破れなくて苦悩するのだとも思う。
どちらにしろ、世界と自分とのあいだに常に言葉が存在するのは事実だ。言葉はただの道具だ、なんてとてもいえないと思うが、どうだろう。
※※※
ごめん、どうしても最後かっこつけてしまう。深い意味はないよ。基本的にこのBlogは自問自答、すべて自分に向けている言葉だと思ってください。
小説が書けない理由
投稿日:2008年09月26日(金)
匂いだ。小説につきまとうある種の匂いが嫌なのだ。その匂いをむりやり言葉にしてみるなら、わざとらしさ、まわりくどさ、うそっぽさの入り交じったものと俺はいう。その匂いが漂いだすと、もう顔をそむけるしかない。そう書いている自分の文章がすでに匂っているのだから、まったく言葉というものは生々しい。その匂いが嫌だから、自分でも書けないのだ。
と、俺の抱いている小説への奇妙な感覚を言葉にしてみた。ちょっと限界。だけど、なんとなくこの匂いってのはわからないかなあ。
寝る。寝れば、また何かわかるだろう。
※※※
くさい台詞ってやつじゃないぜ。
難しいことを簡単にいう
投稿日:2008年09月25日(木)
難しいことを難しい言葉で説明する。難しいことを簡単な言葉で説明する。
簡単なことを難しい言葉で説明する。
簡単なことを簡単な言葉で説明する。
一般的には、難しいことを簡単な言葉で説明できる人ほど優秀であると思われる。俺もそう思う。そういう人には天賦の才を感じる。師と崇めたくなる。どこまでもついて行きたくなる。俺もそういう人になりたい。
だから、なるべく普段から簡単な言葉を使うようにしているのだけれども、難しいことを簡単な言葉で説明するというのは途轍もなく難しいことなのだ。まず、その難しいことを自分が完全に理解している必要がある。理解とはなんぞやという根本的な疑問も沸いてくるかも知れないがとりあえずは置いておく。次に、その難しいことを別の言葉で置き換えるという作業がある。そのためには、説明する相手の言語レベルを見極めるセンスが必要となる。よく言われるのは、小学生にもわかるように説明しよう、だけれども「小学生にもわかる言語レベル」がわかるのは実は凄い人間だと思う。なぜなら、言語レベルとは書いているけれども、それが意味するのは語彙の量ではなく、言語によってもたらされる思考能力の程度だ。つまり、相手の知っている言葉に置き換えるだけでは不十分で、相手の考え方とものの見方までをも考慮しなければならないのだ。
ときどき難しい本に出会う。著者はなるべく簡単な言葉で説明しようとしているのだが、どうにも俺にはわからないときがある。語彙の問題ではない。意味のわからない単語をすべて辞書で調べたとしても、あるいは最初から簡単な単語だけで書かれていたとしても、全体として意味がわからないということがよくあるのだ。これは俺の思考能力の限界を超えているということだ。どんなに言葉を簡単にしても、処理はできないだろう。その考え方を理解できるだけの考え方が俺にはまだないということなのだ。
ちなみに俺がまだ会社員時代に、中学生の職場体験の担当になったことがあった。中学生が夏休みを利用していろいろな仕事を体験してみるというアレだ。俺が若いときにはなかった。その職場体験にくる中学生の子のために、俺は自分の業界の仕組みや商売の基本のようなものをできる限り簡単な言葉で書いた資料を作った。しかし、反応はまったくだった。なんだかわかりませんですううう、という雰囲気がひしひしと伝わってきた。そしてやっと、ああだから職場「体験」なんだな、とわかった。言葉を使った理屈で理解するのが難しいから、体験してもらうんだな、と。
だからこそ、難しいことを簡単な言葉で説明できる人間は凄いと思うのだ。体験や経験を通さずに、言葉の力だけで未知のものを理解してもらう。というより、言葉の力でもって、体験や経験と同じものを得てもらう。これは並大抵のことではないだろう。
で、小説の話になるのだけれども、その並大抵のことではないことをあえてやろうとしているのが小説家ではなかろうか。とんでもなく難しいことを、誰にでもわかる言葉、小説にして読者に伝えている。それが見事な小説は、面白いのだ。もっとも、小説のなかには、簡単なことを難しい言葉で説明しているだけのものもあるだろうけどね。間違った文学観で書かれた俺らの小説とか。
※※※
蛇足。間違った文学観↓
とにかく難しい言葉に置き換えて並べりゃいいさあ。
情景を事細かく描写すればいいさあ。
主人公を悩ませていればいいのさあ。
か?
言葉が言葉を生むのか
投稿日:2008年09月25日(木)
そう考えてみると、なんだかとても安らかな気持ちになってくる。自分の思考のスタンスは、「言語は思考を表現するための道具ではない」「言語によって思考が影響を受ける」「言語が思考そのものだ」を信奉するものだった。しかし、これが小説になるとどうやら「言葉は小説を表現するための道具」(言語を言葉に変えたのはただの雰囲気だよ)としか俺は思っていなかったらしい。まったく応用というものができない人間だな、俺は。
とかいいつつ、なんとなく昔書いていた詩を読み返して見ると、完全に言葉先行・感覚優先のものばかりだった。悪くいえば言葉の響きと雰囲気に頼っただけの詩ばかりなんだけれども、詩を生みだそうという気迫は、小説を書こうとしている今のその比ではない。
もちろん、詩と小説は違うものだけれども、創作する心の根幹までもが違っているわけではないだろう。根っこは同じはずだ。それなのに、詩ではなく小説を書こうとした途端、言葉を単なる道具のように扱い、さらには言語そのものが鬱陶しいルールの塊にしか見えなくなったのは、致命的だ。
敬愛する花村萬月先生のお好きな「言葉に淫する」という言い回し、まさにその意味をまるでわかっていなかったのだろうか、俺は。
寝る。
竹の子書房
Amazon
カテゴリー
レコメンド
人気記事
リンク
最新記事
カレンダー
プロフィール
メールでのご連絡は benzine100@gmail.こむ スパム対策なのでこむをcomにかえてください。
ブログ内検索
アクセス解析
忍者アナライズ
お知らせ
★☆★本に掲載されました★☆★
■([か]2-5)てのひら怪談 壬辰: ビーケーワン怪談大賞傑作選 (ポプラ文庫 日本文学)
■3.11 心に残る140字の物語
■てのひら怪談 辛卯―ビーケーワン怪談大賞傑作選 (ポプラ文庫)
■てのひら怪談 庚寅―ビーケーワン怪談大賞傑作選 (ポプラ文庫)
=====↓読者投稿怪談が掲載されています↓=====
■怪談実話系ベスト・セレクション (文庫ダ・ヴィンチ)
■怪談実話系 4―書き下ろし怪談文芸競作集 (MF文庫 ダ・ヴィンチ ゆ 1-4)
――巻末の読者投稿怪談に採用されました♪
★Twitter始めました
こちら→http://twitter.com/oboroose
★リレー小説に参加しています。
★怪談投稿しています。(ペンネーム:小瀬朧)
こちら→WEB幽